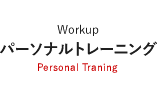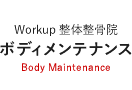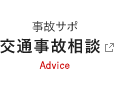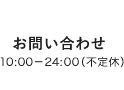食中毒とは?原因と予防を知って夏を安心して過ごそう

蒸し暑い季節になると特に注意が必要なのが食中毒です。食中毒は、食べ物に含まれる細菌・ウイルス・毒素などが体内に入ることで引き起こされる急性疾患で、主な症状は吐き気・下痢・腹痛・発熱です。特に夏場や災害時には発生しやすいため、日頃から正しい知識を持って予防することが大切です。
食中毒の主な原因
食中毒にはさまざまな原因があり、大きく以下に分類されます。
| 原因 | 具体例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 細菌 | サルモネラ、O157、リステリア | 夏に多発。加熱不足の肉や生卵で感染。 |
| ウイルス | ノロウイルス、A型肝炎 | 冬場に多い。少量のウイルスでも感染力が強い。 |
| 自然毒 | フグ毒、貝毒、毒キノコ | 自然由来。強い毒性を持ち、重症化することも。 |
| 化学物質 | ヒスタミン(魚の不適切保存) | アレルギー様症状を引き起こす。 |
| 寄生虫 | アニサキス | 生魚(特にサバ・イカ)に多く、激しい腹痛を伴う。 |
季節ごとの注意点
- 夏(6〜9月):高温多湿により細菌が増殖しやすく、生肉・魚・惣菜の管理に注意。
- 冬(11〜2月):ノロウイルスによる集団感染が多発。牡蠣や二枚貝の生食は特に注意。
家庭でできる食中毒予防の三原則
- 細菌をつけない:生肉と野菜・調理済み食品を別々に扱い、まな板や包丁を分ける。
- 細菌を増やさない:冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下を維持。常温放置を避ける。
- 細菌をやっつける:中心部まで十分に加熱(75℃以上で1分以上が目安)。
買い物から保存までの注意点
- 生鮮食品は最後に購入し、保冷バッグを活用。
- 肉や魚はドリップ(液体)が漏れないよう袋を分ける。
- 冷蔵庫は詰め込みすぎず、7割程度に保つ。
調理時のポイント
- 生肉・魚はよく加熱し、中心部の色が変わるまで火を通す。
- 包丁やまな板は使用後すぐに洗浄・消毒。
- 調理済みの食品は2時間以内に冷蔵保存。
外食やお弁当での注意
外食時や持ち運びするお弁当でも注意が必要です。
- 刺身や生ガキは新鮮なものを選ぶ。
- お弁当は完全に冷ましてから蓋をする。
- 梅干しや酢飯を活用すると菌の増殖を抑えやすい。
症状が出たときの対応
軽度の場合
- 経口補水液で水分・電解質を補給。
- 消化に良い食事(おかゆ、バナナ、うどん)を少しずつ。
- 下痢止め薬は自己判断で使用しない。
重度の場合
- 水分すら摂れない激しい嘔吐。
- 血便や高熱、激しい腹痛。
- 意識障害や呼吸困難。
これらの症状がある場合はすぐに医療機関を受診してください。
まとめ
食中毒は正しい保存・調理・食習慣を守ることで予防できます。特に夏は細菌による食中毒が多発するため、日常生活の中で「つけない・増やさない・やっつける」を徹底することが重要です。症状が出た場合は自己判断せず、速やかに医療機関を受診しましょう。